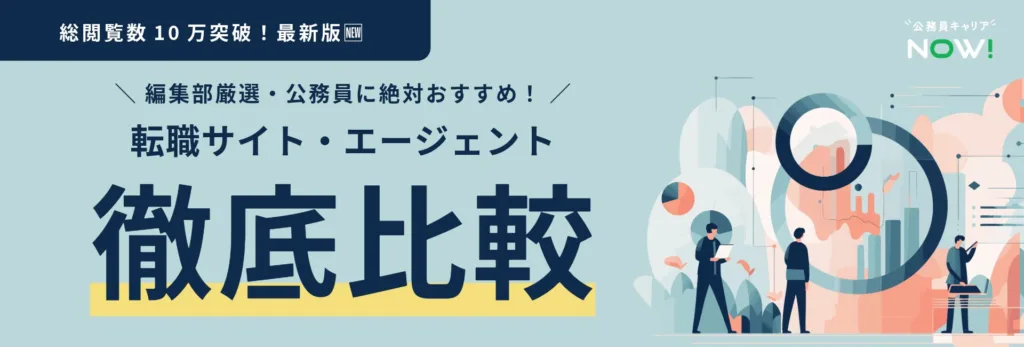はじめに:なぜ「公務員のスキルアップ費用」に注目するのか
近年、公務員に対する社会の期待は多様化・高度化しています。少子高齢化、地域経済の再生、防災・福祉・教育など多岐にわたる行政課題に対応するため、従来の業務範囲を超えたスキルが求められるようになっています。
こうした状況の中で、スキルアップやリスキリングへの関心が高まりを見せていますが、実際には「時間がない」「制度が活用できない」「費用がかかる」といった理由で、十分な自己投資ができていない職員も少なくありません。
本記事では、公務員のスキルアップにかかる費用や時間の実態を、最新の調査データをもとに明らかにしつつ、制度面の課題や今後の可能性について考察します。
課題背景と制度整理
公務員のスキルアップは、人事評価や昇任試験、特定業務の専門性強化など、組織内の職務遂行能力向上に直結します。国家公務員・地方公務員を問わず、各組織には階層別研修や業務別研修などが制度として整備されています。
しかしながら、以下のような制度的・実務的課題が指摘されています:
- 研修の目的が「形式的」になっており、現場で活かされにくい
- 外部講座の受講や資格取得に対する支援が限定的
- キャリア形成を個人任せにしている自治体も多い
たとえば、ある自治体では、外部研修や大学院通学への「費用補助制度」は設けられているものの、申請条件が厳しく、実質的に利用できる職員が限られているという声もあります。
さらに、公務員のキャリア制度そのものが「年功序列型」から「専門職志向型」へとシフトする中で、個々人が自ら学び直し、キャリアを設計する必要性が増しています。
そのためには、組織側の制度整備だけでなく、職員一人ひとりの意識変革と、費用面のハードルを下げる支援が求められています。
実態データ:費用・時間・頻度などの推計
2025年4月に日本総合研究所が発表した「公務員のスキルアップに関する意識・実態調査」によると、全国の地方公務員1,500名超を対象にした調査で、以下のような結果が明らかになりました。
- 年間の自己投資額が「1万円未満」の職員は全体の38.4%
- 「1〜3万円未満」が23.2%、「3〜5万円未満」が15.9%
- 一方で「10万円以上」自己投資している層も7.4%存在
このデータは、公務員の多くが自己投資を抑え気味である一方、一定層が積極的に学習や資格取得に取り組んでいることを示唆しています。
また、学習に充てている1週間あたりの時間については、以下の傾向が見られます。
- 「0時間〜30分未満」:34.7%
- 「30分〜1時間未満」:22.6%
- 「1時間〜3時間未満」:27.1%
- 「3時間以上」:15.6%
公務員の勤務時間が比較的長く安定している一方で、プライベートな時間における学習活動は限定的であることがわかります。
学習内容の傾向としては、以下のジャンルが挙げられます。
- IT・DX系スキル(Excel、統計、Pythonなど)
- コミュニケーション・マネジメント研修
- 国家資格(キャリアコンサルタント、社労士など)
特に若手職員層では、キャリアの多様化や将来の転職も見据えて、民間企業でも通用するスキルを身につけたいというニーズが顕在化しています。
参考記事 ▶︎ 公務員のマネジメント能力向上に必要なスキルの明確化に関する報告書を公表|株式会社日本総合研究所、株式会社グロービス
課題整理:公務員が抱えるスキルアップの障壁
スキルアップに対する意識が高まっている一方で、行動に移せていない職員が多いのも現実です。日本総研の調査や自治体ヒアリングから見えてきた主な障壁は以下のとおりです。
① 費用面の不安
公務員の給与水準は安定しているものの、家計に占める教育・学習費の優先順位は低くなりがちです。特に、30〜40代の子育て世代においては、自己投資よりも生活費・教育費が優先されやすく、学習に対する金銭的余裕が持てないという声が多く聞かれます。
② 制度の理解不足
多くの自治体では、外部研修や大学通学の「休職制度」や「学費補助制度」が存在しますが、その周知が不十分なケースも多く、「存在は知っているが使い方がわからない」「申請の手間が面倒」といった理由で利用が進んでいません。
③ 時間の確保が難しい
職場によっては繁忙期が長期化しており、「勉強したい気持ちはあるが、残業後に学習時間を確保するのが難しい」という課題があります。とりわけ、窓口業務や現場対応の多い部署においては、イレギュラー対応が学習計画の障害になることもあります。
④ モチベーション維持の難しさ
「何のために学ぶのか」が明確でない場合、学習が継続しにくいという問題もあります。目先の昇任試験対策だけでなく、長期的なキャリアデザインの中でスキルアップをどう位置づけるかが不明確なままだと、継続意欲の低下につながりやすくなります。
これらの課題を乗り越えるには、制度の改善だけでなく、職員一人ひとりの目的意識や時間管理の工夫、上司や同僚による理解・支援といった「環境づくり」も不可欠です。
成功事例・活用可能策
公務員の中には、制度や環境の制約を乗り越え、着実にスキルアップを実現している事例も多く存在します。ここでは、いくつかの代表的な成功パターンを紹介しつつ、実践可能なアプローチをご紹介します。
① 補助制度の積極活用
ある自治体では、通信制大学での学位取得を目指す職員が、自治体の「自己啓発休業制度」を活用しながら、3年間で修士号を取得しました。制度の内容を自ら調べ、人事課と丁寧に交渉したことが成功の鍵でした。また、eラーニングサービスや語学講座に対する補助金を活用し、TOEICスコアを大幅に向上させた若手職員もいます。中には、補助制度を活用して業務時間外に資格講座を受講し、行政書士試験に合格した例もあります。
② 隙間時間を活かした習慣化
スキルアップを継続できている職員の多くは、「毎日15分だけ学習する」といった習慣化に成功しています。通勤中の読書、昼休みの動画視聴、退庁後のオンライン講座受講など、時間を細切れに活用する工夫が見られます。
③ チームでの学習や情報共有
ある部署では、若手職員が自主的に「学びのシェア会」を週1回開催し、おすすめの本や記事、講座の紹介を行っています。上司も巻き込み、職場全体での学習文化が醸成されることで、モチベーションの維持にもつながっています。
④ 民間講座・資格の選定ポイント
費用対効果の高い講座選びのために、職員が活用しているポイントは以下の通りです:
- 自分の業務や転職検討の際の領域に直結する内容か
- 自己啓発支援制度など費用補助などがあり得るか
- 録画受講やスマホ対応など、学習しやすい形式か
- 同属性の方の受講実績や評判があるか
必要以上に高額な講座を選ぶのではなく、1万円前後の学習教材や短期講座を活用し、「できるところから始める」姿勢が、多くの成功事例に共通しています。
おすすめのスキルアップサービス(PR)
忙しい公務員の方でも無理なく取り組めるよう、時間や費用を抑えながら学習可能なスキルアップサービスを厳選してご紹介します。
1. ベルリッツ(Berlitz)
Berlitz が運営、英語での公的対応や海外研修に備えたい方に最適。対面・オンラインの両方に対応しており、実践的な会話力が身につきます。TOEIC対策や業務英語など、目的別のコースも充実しています。
2. GLOBIS 学び放題
株式会社グロービス![]() が提供する、政策立案やプロジェクトマネジメントに必要なビジネススキルを体系的に学べるサブスク型学習サービス。経営戦略・思考法・リーダーシップなどを網羅し、月額制でコスパも良好。1講座5〜10分で完結するため、隙間時間に最適です。
が提供する、政策立案やプロジェクトマネジメントに必要なビジネススキルを体系的に学べるサブスク型学習サービス。経営戦略・思考法・リーダーシップなどを網羅し、月額制でコスパも良好。1講座5〜10分で完結するため、隙間時間に最適です。
3. AI×webライティング【WILL】
WILL![]() が提供する、AIライティング未経験者でも安心して始められるオンライン完結型サービスです。広報・情報発信を担う公務員におすすめ。AIを活用して文章力や構成力を高めることができ、Web記事の作成やSNS運用などのスキル向上に役立ちます。
が提供する、AIライティング未経験者でも安心して始められるオンライン完結型サービスです。広報・情報発信を担う公務員におすすめ。AIを活用して文章力や構成力を高めることができ、Web記事の作成やSNS運用などのスキル向上に役立ちます。
4. ウェブ解析士認定講座
一般社団法人ウェブ解析士協会![]() が運営、自治体DXや情報戦略を担う部署におすすめ。Webサイトのアクセス解析やデータ活用を学べる講座で、広報や政策のPDCAに役立つ知識が習得できます。オンライン対応で受講しやすく、全国の自治体でも導入実績多数。
が運営、自治体DXや情報戦略を担う部署におすすめ。Webサイトのアクセス解析やデータ活用を学べる講座で、広報や政策のPDCAに役立つ知識が習得できます。オンライン対応で受講しやすく、全国の自治体でも導入実績多数。
5. パソコンスクールISA
株式会社アイエスエイ![]() が運営するパソコンスクール。ExcelやPowerPointなど、日常業務に不可欠なPCスキルを強化。個別指導とオンライン受講に対応しており、初心者でも安心。自治体との連携実績もあり、導入研修としても活用されています。
が運営するパソコンスクール。ExcelやPowerPointなど、日常業務に不可欠なPCスキルを強化。個別指導とオンライン受講に対応しており、初心者でも安心。自治体との連携実績もあり、導入研修としても活用されています。
6. テックキャンプ
株式会社div が運営するプログラミング初心者からでも実践的なスキルを身につけられる総合ITスクール。HTML/CSSやRubyなどの基礎から、AI・データ分析まで幅広く学習可能です。特に「公務員から民間へのキャリア転換」や「副業スキル獲得」を目指す方におすすめ。通学・オンラインの両方に対応しており、専属メンターのサポートも手厚いため、途中で挫折しにくいのが特徴。
7. キャリアコンサルタント養成講習
一般社団法人地域連携プラットフォーム![]() が提供する国家資格のキャリアコンサルタントの育成講座です。教育・福祉・雇用などの領域で住民支援に携わる職員にもおすすめ。取得することで相談支援能力が向上し、組織内外でのキャリア支援活動にも役立ちます。
が提供する国家資格のキャリアコンサルタントの育成講座です。教育・福祉・雇用などの領域で住民支援に携わる職員にもおすすめ。取得することで相談支援能力が向上し、組織内外でのキャリア支援活動にも役立ちます。
編集部からのひとこと
これらのサービスはいずれも、自治体によっては「自己啓発支援制度」や「研修補助金制度」の対象となる場合があります。費用補助が受けられる可能性があるため、所属部署に確認してみることをおすすめします。
また、スキルアップを本気で進めたいなら、1つのサービスだけに絞らず、複数の講座やプラットフォームに登録するのがおすすめです。
特に忙しい公務員の方にとっては、「自分に合った学び方」を見つけることが継続のカギとなります。
スキルアップは、「やる気がある時に環境を整えること」が最も大切です。
まずは気になるサービスを2~3つピックアップして、無料体験やカウンセリングを受けてみることから始めましょう。
まとめ:戦略的スキルアップのすすめと今後に向けた展望
公務員のスキルアップは、「やる気がある人だけが取り組むもの」ではなく、これからの行政組織にとって不可欠な要素です。政策の複雑化や住民ニーズの多様化に対応するには、個々の職員が専門性と柔軟性を兼ね備える必要があります。
今回見てきたように、自己投資の実態は決して高いとは言えず、制度面・意識面ともに課題が残るのが現状です。しかし一方で、制度を活用し、創意工夫を凝らしてスキルアップを実現している職員の姿も確かに存在します。
これからの時代、以下の3点が重要なキーワードとなるでしょう:
- 「小さく始める」自己投資
- 制度を「知って使う」情報感度
- 学びを「職場に還元する」意識
自治体や組織としても、単なる研修制度の整備にとどまらず、学ぶ意欲を支える文化づくりや、スキルを活かせるポスト設計が求められています。
「学び続ける公務員」が当たり前になる社会に向けて、まずはできることから一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。
\ スキルアップで成長しよう! 『公務員向け スキルアップガイド2025』 /