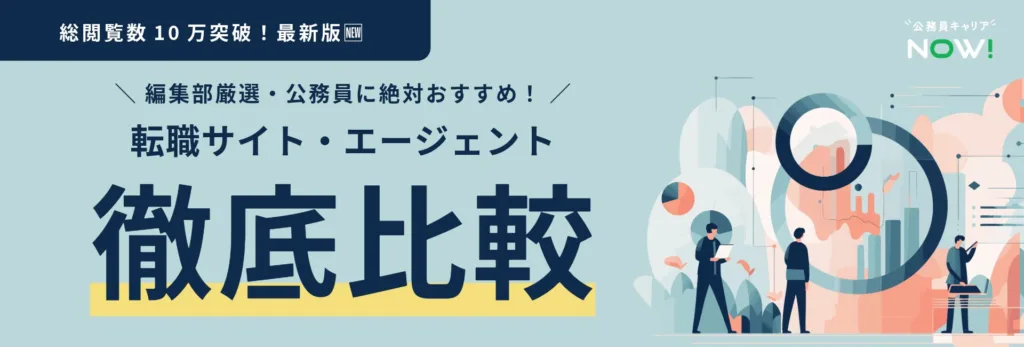公務員のボーナスはいつ?国家公務員・地方公務員の違いと支給額を徹底解説!
「公務員のボーナスっていつ支給されるの?」「国家公務員と地方公務員で違いはあるの?」という疑問を抱く方のために、この記事ではボーナスの支給時期・支給額・人事院勧告との関係性などを、国家公務員・地方公務員に分けて詳しく解説します。
公務員のボーナスは年2回:6月と12月
国家・地方問わず、ボーナスは年2回支給されます。
- 夏季賞与(6月末):多くの自治体や機関で6月30日前後
- 冬季賞与(12月初旬〜中旬):12月10日前後が中心
ただし支給日はそれぞれの自治体や省庁によって数日前後することがあります。
国家公務員のボーナス:概要と支給実態
① 支給の根拠:人事院勧告に基づく
国家公務員の給与・ボーナスは、「人事院勧告」に基づいて決定されます。これは、民間企業の水準と均衡を保つために毎年7月に発表される俸給(基本給)見直し提案であり、賞与支給月数もこの勧告に含まれます。
② 支給日とスケジュール
- 夏の支給日:6月30日が原則(前倒しあり)
- 冬の支給日:12月10日が多い(前倒しあり)
③ 支給額の目安(2024年度例)
年間の支給月数:約4.4ヶ月分
| 階級 | 年間賞与目安 |
|---|---|
| 一般職(20代) | 約80万円 |
| 主任級(30代) | 約120万円 |
| 課長補佐級(40代) | 約160万円 |
| 課長級(50代) | 約200万円以上 |
④ 支給条件と注意点
- 支給日に在職していないと受給不可
- 長期休職中の場合、減額されるケースあり
地方公務員のボーナス:自治体ごとの違いと傾向
① 基本は国家公務員に準ずる
地方公務員も原則として国家公務員の人事院勧告に準じたボーナス支給を行います。ただし、条例によって支給率を調整できるため、自治体によって若干の差があります。
② 支給日とパターン
- 多くの自治体:6月30日・12月10日支給
- 一部:12月15日、または翌週支給の例もあり
③ 支給額の事例(都道府県別平均:2024年)
| 自治体 | 年間支給額(平均) |
|---|---|
| 東京都 | 約155万円 |
| 大阪府 | 約148万円 |
| 広島県 | 約142万円 |
| 地方小規模自治体 | 約120〜130万円 |
④ 教員・警察・消防などの特殊職
地方公務員の中でも教職員、警察官、消防官などの職種は支給月数や手当計算がやや異なる場合があります。基本的には条例・労使協定に準じます。
公務員のボーナス支給にまつわるQ&A
Q. 支給されないケースはある?
あります。以下のようなケースでは支給対象外となることがあります:
- 支給日直前に退職した
- 産前・育休・病休などで長期間無給だった
Q. 転職したらボーナスはどうなる?
転職時期が支給日前であれば、退職元からボーナスは支給されません。公務員から民間、またはその逆でも同様の扱いです。
民間企業との違いは?

民間企業のボーナスは「業績連動型」が一般的であり、会社の利益状況により増減します。一方、公務員は国家財政や人事院の調整により支給されるため、以下のような特徴があります:
- 極端に減額されるリスクが低い
- 支給額の見通しが立てやすい
- 定年までの支給実績が安定している
ボーナス制度の基本的な違い
| 項目 | 公務員 | 民間企業 |
|---|---|---|
| 支給回数 | 年2回(6月・12月) | 年2回が一般的(夏・冬) |
| 支給基準 | 人事院勧告・条例に基づく | 会社の業績・個人評価に連動 |
| 金額の安定性 | 非常に高い | 業績により変動 |
| 評価制度 | 基本的に年功序列/定期昇給 | 成果主義・人事評価による差 |
年代別・賞与額の比較表(年額・万円)
-1-png.webp)
詳細
| 年代 | 国家公務員 | 地方公務員 | 中小企業 | 大手企業 |
|---|---|---|---|---|
| 20代前半 | 70 万円 | 75 万円 | 50 万円 | 80 万円 |
| 20代後半 | 90 万円 | 95 万円 | 60 万円 | 100 万円 |
| 30代前半 | 110 万円 | 115 万円 | 70 万円 | 120 万円 |
| 30代後半 | 130 万円 | 135 万円 | 80 万円 | 140 万円 |
| 40代前半 | 150 万円 | 155 万円 | 90 万円 | 160 万円 |
| 40代後半 | 170 万円 | 175 万円 | 95 万円 | 170 万円 |
| 50代以上 | 190 万円 | 195 万円 | 100 万円 | 180 万円 |
| 平均 | 130 万円 | 135 万円 | 77.9 万円 | 135.7 万円 |
| 中央値 | 130 万円 | 135 万円 | 80 万円 | 140 万円 |
20代〜30代は民間大手がやや優位
20代では民間大手企業の賞与額が公務員をやや上回る傾向にあります。特に「20代後半」でその差が顕著で、大手企業の平均賞与は100万円に達します。一方、中小企業では60万円程度に留まっており、公務員との格差も見られます。
40代以降は公務員が安定して上昇
30代後半以降は、国家公務員・地方公務員の賞与額が安定的に上昇していき、「40代後半」で地方公務員は175万円に到達します。特に「50代以上」になると、国家公務員190万円、地方公務員195万円と、民間大手よりも高水準となっています。
平均・中央値は公務員が優勢
平均・中央値ともに、公務員(国家・地方)は民間企業よりも高い結果に。国家公務員の平均賞与は130万円、地方公務員は135万円と、いずれも安定感があることがわかります。
評価方法の違い:公務員は年功・民間は成果重視
公務員の評価制度
公務員の評価制度は「職務遂行能力」や「勤務態度」「協調性」などを重視する傾向があり、点数化されてもその評価が直接賞与に反映されることは少ないです。結果として、勤続年数や役職が主な増額要素となります。
民間企業の評価制度
民間企業では、定量目標(売上、成果、KPI)に加えて、上司の定性評価、同僚との相対比較などによって賞与が決定します。評価結果によっては、同じ年次でも数十万円の差がつくケースもあります。
安定性と将来性の違い
公務員:安定的で計画が立てやすい
ボーナス支給額は国の人事院勧告や条例によって毎年設定されるため、予測が立てやすく、ライフプランや住宅ローンの計画も立てやすい点が大きなメリットです。
民間企業:成長性はあるが不安定
業績によって大きな変動があるため、不景気時には「賞与ゼロ」や「カット」のリスクもあります。一方で成果を出せば飛躍的に報酬が上がる可能性もあり、上昇志向のある人には魅力的な環境です。
結局はそれぞれの”価値観”で変わる
① 【安定性 vs 成果主義】求める価値観が異なる
公務員の賞与は「勤続年数・等級」による安定的な加算が特徴。長期的な見通しを持ちやすい。
民間企業の賞与は「業績・個人評価」による変動制。成果を出せば短期的に高額も可能。
👉 安定収入を重視する人には公務員、短期でのリターンや自己成長を求める人には民間企業が適しており、本人の価値観によって“良し悪し”は変わる。
② 【年齢・キャリア段階で優劣が入れ替わる】
若年層(20〜30代)では、民間大手企業の賞与が高い傾向。
40代以降になると、公務員の方が安定的に賞与が上昇していく構造。
👉 年代によって有利不利が逆転するため、「いつ・どの時点を見るか」で結論が異なる。
③ 【中小企業 vs 大手企業、公務員内の格差も存在】
民間企業でも大手と中小で賞与額に大きな差がある(例:年額80万円 vs 180万円)。
公務員でも、国家と地方、自治体ごとに賞与水準にばらつきがある。
👉 「民間 vs 公務員」の2軸だけでは語れない複雑性があり、一律に比較するのは困難。
④ 【将来の変動要素が読みにくい】
民間企業:景気後退や事業再編で賞与削減・廃止のリスクあり。
公務員:人事院勧告や財政難での見直し(支給月数減)などの可能性もゼロではない。
👉 どちらにも将来的な不確実性が存在するため、現時点での「優劣」はあくまで暫定的なもの。
まとめ
公務員と民間企業を賞与(ボーナス)を比較する際、一概にどちらが良いとは言えません。
公務員は年功序列や等級制度に基づき、安定した賞与が支給される傾向があり、特に40代以降は民間企業よりも高額になるケースが多く見られます。
一方、民間企業では業績や個人の成果によって賞与額が大きく変動し、特に若年層では大手企業に勤めることで高額な賞与を得る可能性もあります。しかし中小企業では支給額が低めにとどまるなど格差も大きく、また将来の経済情勢や制度変更による影響も見逃せません。
結局のところ、賞与の「良し悪し」はその人の価値観やキャリア段階、勤務先の特性によって異なります。安定を取るか、成果主義に挑戦するか——賞与だけで判断せず、ライフプラン全体を見据えた選択が重要です。