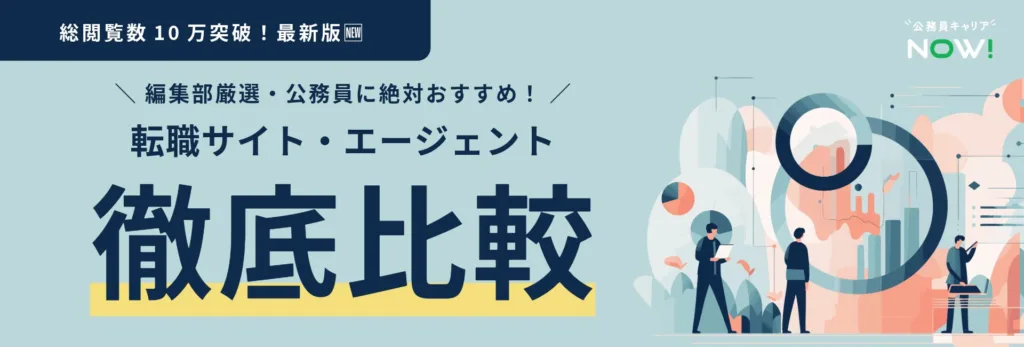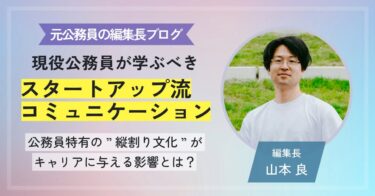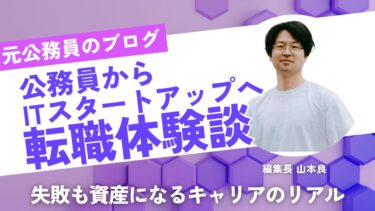公務員が株式投資・投資信託を学ぶべき理由
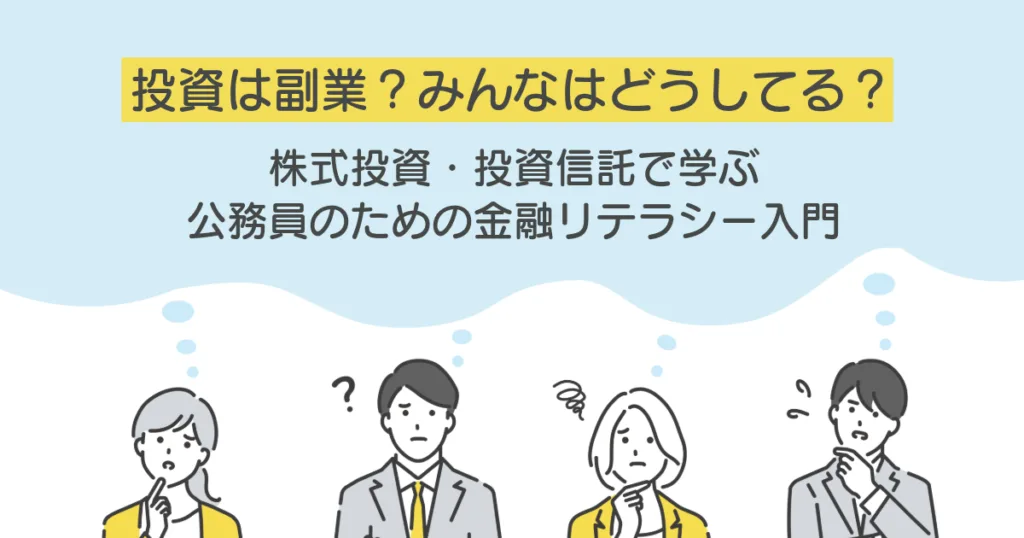
公務員は「安定した職業」として多くの人から羨望の眼差しを向けられます。しかし近年は、将来に対する不安を抱える現役公務員も少なくありません。年金や退職金の制度は今後も変動の可能性があり、さらに物価上昇(インフレ)や社会保障費の増加など、将来の生活に影響する要因が数多く存在しています。
こうした背景から、いま公務員に求められているのは「職業的な安定」だけに頼らず、自ら資産を守り育てる力=金融・マネーリテラシーを身につけることです。そのための有効な手段が、株式投資や投資信託です。これらは副業にはあたらないため、法的に安心して取り組める「資産形成の方法」として広く活用されています。
株式投資や投資信託を学ぶことは、単にお金を増やす手段を得るだけではありません。経済や社会の動きを理解し、リスクとリターンの関係を判断できる力を養うことにもつながります。これは将来の老後資金やライフプランの設計に直結するだけでなく、日常の家計管理や仕事上の意思決定にまで活きてきます。
つまり、株式投資や投資信託を学ぶことは、「公務員としての安定にプラスして、自ら未来をコントロールする力を手に入れること」なのです。これからの時代を安心して生き抜くために、公務員こそ早めに資産運用を学び始めるべきだといえるでしょう。
公務員にとって株式投資・投資信託は副業になる?
「株式投資や投資信託をすると副業禁止規定に違反するのでは?」と考えている公務員の方は少なくありません。しかし、これは大きな誤解です。法律上、公務員が禁止されているのは労働や経営を通じて収入を得る行為であり、純粋な資産運用である投資は副業にはあたりません。
詳しく解説すると、国家公務員法と地方公務員法には以下のような規定があります。
- 国家公務員法第103条:「職員は、営利を目的とする私企業の役員等となり、または自ら営利企業を営んではならない」
- 国家公務員法第104条:「営利企業以外の団体において報酬を得る事業・事務に従事する場合、内閣総理大臣等の許可が必要」
- 地方公務員法第38条:「職員は、任命権者の許可なく営利企業の役員となったり、自ら営利企業を営んだり、報酬を得て事業・事務に従事してはならない」
これらの条文が示しているのは、営利企業で働いたり経営に参画したりすることが制限されているという点です。つまり、「労働や経営」による収入が副業とみなされるのです。
一方で、株式投資や投資信託は資産運用の一環であり、労働や経営活動に従事するものではありません。証券会社を通じて株式や投資信託を購入する行為は「自分の資産をどう管理・運用するか」という判断にすぎず、国家公務員法や地方公務員法が定める副業禁止には該当しません。そのため、公務員が証券口座を開設して株式や投資信託を運用することは、法的に認められています。
ただし、例外として注意すべきケースもあります。
- 勤務先と利益相反関係にある企業の株式を保有する場合
- 未公開情報を利用したインサイダー取引を行った場合
- 投資顧問業のように第三者に有償で助言・事業として行う場合
- 他者の資産運用を代理で行う場合(例:家族や知人の口座を代わりに運用し収益を得るなど)
これらは副業や違法行為に該当する可能性がありますが、通常の株式投資や投資信託の購入・保有であれば心配は不要です。むしろ、金融リテラシーを高め、将来の生活設計を考える上で大切な取り組みとなります。
結論として、「株式投資=副業」と考える必要はなく、公務員でも資産形成のために安心して投資を始められるのです。
そもそも資産運用とは?

「資産運用」と聞くと、株や投資信託など専門的で難しいイメージを持つ方も多いかもしれません。しかし、資産運用の本質はとてもシンプルで、自分が持っているお金を将来に備えて増やしていく工夫のことを指します。
銀行に預けているだけでは、低金利の時代にお金はほとんど増えません。むしろ、物価上昇(インフレ)が続けば、同じ金額でも将来の購買力は下がってしまいます。そこで重要になるのが、お金を「働かせる」発想です。
資産運用にはさまざまな方法がありますが、大きく分けると以下のような手段があります。
- 預貯金:安全性は高いが利息はほとんどつかない
- 株式投資:リスクはあるが、大きなリターンも期待できる
- 投資信託:少額から始められ、分散投資によりリスクを抑えられる
- 債券・不動産:安定的な収益を狙えるが、まとまった資金が必要な場合もある
大切なのは、「短期的に儲ける」ことではなく、長期的にコツコツ増やしていくことです。特に公務員のように安定した収入基盤を持っている方にとって、資産運用は将来の安心につながる有効な選択肢といえるでしょう。
次のセクションでは、資産運用の代表的な方法である株式投資と投資信託の違いについて、より詳しく解説していきます。
株式投資と投資信託の違いを学ぼう!
資産運用を始める公務員にとって、まず理解すべきは株式投資と投資信託の違いです。この2つはよく並べて語られますが、仕組みやリスクの性質、学習のポイントが大きく異なります。
株式投資の特徴
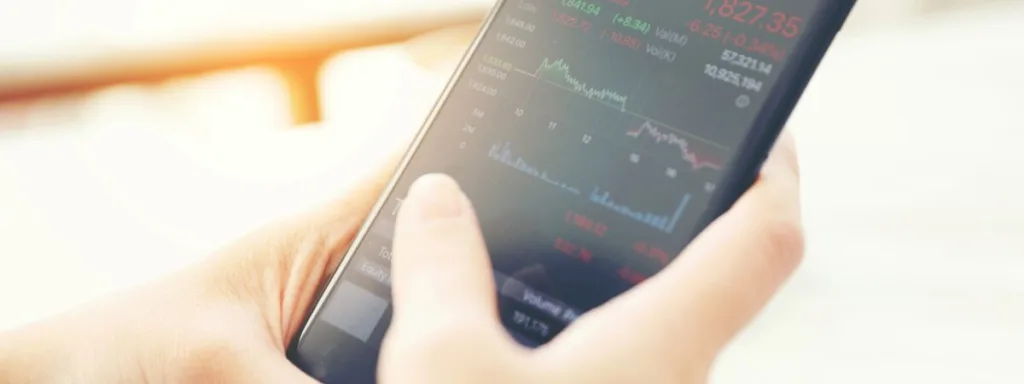
株式投資(個別株への投資)とは、個別の企業の株式を購入し、その会社の一部を所有することを意味します。株主となることで以下のような利益を得る可能性があります。
- 値上がり益(キャピタルゲイン):購入した株価が上昇したときに売却することで得られる利益
- 配当金(インカムゲイン):企業が利益を還元する形で支払う分配金
一方で、株式投資は個別企業の業績や市場動向に大きく左右されるためリスクが高いのも特徴です。リターンが大きい反面、短期間で価格が急変する可能性があるため、企業研究や経済ニュースを継続的にチェックする必要があります。
株式投資を始めるには、まず証券会社で口座を開設します。スマホやインターネットから簡単に申し込めるネット証券(例:楽天証券、松井証券、SBI証券)や、店舗型でサポートが充実している大手証券会社(例:野村證券)など、一般的に認知度の高い会社を利用するのが一般的です。口座に入金したら、取引アプリやWebサイトから銘柄を検索して購入できます。
最低購入単位(通常100株)から取引可能ですが、ネット証券では1株単位で購入できるサービスもあり、少額からの投資も可能です。
投資信託の特徴
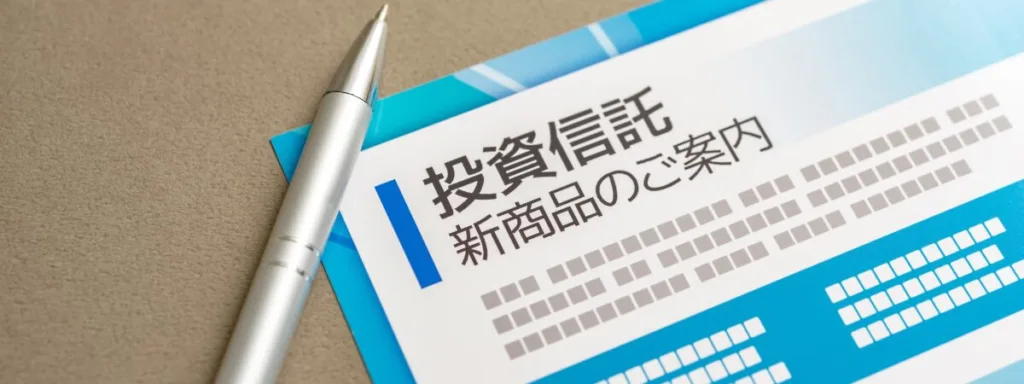
投資信託は、複数の投資家から集めた資金を専門の運用会社がまとめて管理し、株式や債券などに分散投資する仕組みです。初心者にとっては以下の点で取り組みやすい投資手段といえます。
- 少額から始められる:毎月1,000円からの積立が可能
- 分散投資によるリスク軽減:複数の銘柄や地域に分けて投資するため、一つの企業の業績悪化による影響が小さい
- プロによる運用:投資の専門家が投資先を選定・運用してくれる
ただし、投資信託には信託報酬(運用手数料)がかかるため、長期的に保有する場合はコスト管理も重要になります。
投資信託も証券会社や銀行で口座を開設すれば購入できます。ネット証券(楽天証券やSBI証券など)では数百円から積立できるサービスがあり、初心者に人気です。大手証券会社(野村證券、大和証券など)でも取り扱いはありますが、ネット証券は商品数や手数料面で選ばれることが多いです。購入方法はシンプルで、対象の投資信託を選び、毎月の積立額や購入日を設定するだけ。自動で引き落とされるため、忙しい公務員でも無理なく継続できる仕組みです。
どっちがいいの?
株式(個別株)投資と投資信託では仕組みやリスク、始めやすさ・初心者に向いているかどうかが異なります。一般的な見解となりますが、以下の表で比較してみましょう。
| 項目 | 株式投資 | 投資信託 |
|---|---|---|
| 投資対象 | 個別企業の株式 | 複数の株式や債券などをまとめた金融商品 |
| 運用方法 | 自分で企業を選び、売買のタイミングを決定 | 運用会社が分散投資を行い、プロが運用 |
| リスク | 個別企業の業績や市場に左右されやすい | 分散投資によりリスクは比較的低め |
| リターン | 大きな利益を狙える可能性がある | 安定的だが株式投資より控えめ |
| 売買(現金化)の タイミング | 取引時間内なら即日売買可能(株式市場の取引時間に準ずる) | 解約申込後、現金化まで数日かかる(通常2〜5営業日) |
| 必要な知識 | 株式市場(企業・経済)・原理の理解が必要 | 基本的な仕組みを理解すれば初心者でも取り組みやすい |
| 運用手数料 | 売買ごとに取引手数料(証券会社による) | 購入時手数料+運用管理費用(信託報酬)+解約時コストが発生する場合あり |
| 税金 | 売却益や配当に対して約20.315%の課税(特定口座で自動計算可能) | 分配金や売却益に同じく約20.315%課税(NISAを利用すれば非課税枠あり) |
| 始めやすさ | ある程度の資金と分析力が必要 | 少額(1,000円〜)からコツコツ積立可能 |
| 向いている人 | 自分で判断して大きなリターンを狙いたい人 | コツコツと安定的に資産形成をしたい人 |
株式投資と投資信託にはそれぞれ異なる特性と魅力があります。どちらが正しい、優れているということではなく、自分のライフスタイルやリスク許容度、投資の目的に合った方法を見つけることが大切です。大きなリターンを狙いたい人には株式投資、安定的にコツコツと資産形成したい人には投資信託、そして両者をバランスよく組み合わせる選択肢もあります。重要なのは、自分自身に合った投資スタイルを確立することです。
編集部のひとこと:NISAを活用した投資信託とは?

NISA(ニーサ)とは、「少額投資非課税制度」のことで、株式や投資信託などの運用益にかかる税金を非課税にできる国の制度です。通常、投資で得た利益には約20.315%の税金が課されますが、NISAを活用すれば一定の投資枠内で非課税となり、効率的に資産を増やすことができます。
2024年からは「新NISA」として制度が拡充され、非課税保有限度額が大幅に拡大されました。また、これまでのNISAは期間制限がありましたが、新制度では非課税期間が無期限となり、より長期的な資産形成に適した仕組みに改善されています。
NISAには大きく分けて以下の投資枠があります。
- つみたて投資枠:長期・積立・分散投資を目的とした枠。金融庁が認めた投資信託などに限定。
- 成長投資枠:株式やETFなど、幅広い金融商品に投資できる枠。積極的な運用をしたい人向け。
公務員にとってもNISAは副業ではなく、合法的に認められた資産運用の方法です。給与収入にプラスして、将来の生活設計を支える有力な選択肢として活用できます。「税金を気にせずに投資を学びながら資産形成できる」――それがNISAの最大の魅力です。
ただし、投資はあくまで自己責任。短期的な利益を狙うのではなく、長期・積立・分散の基本を守ることが大切です。その過程で上記に挙げたような金融リテラシー向上の学習を通し、「リスクとリターンの関係」「世界経済の流れ」「家計管理と投資のバランス」といった知識を身につけていくことが、現代を生きる社会人にとってとても大事な要素になります。
💰 参考 ▶︎ NISAを知る:NISA特設ウェブサイト|金融庁
マネーリテラシーを高める学習の重要性

資産運用は「お金を増やす」ことだけが目的ではなく、正しい知識を身につけて自分で判断できる力=マネーリテラシーを育むことが本質です。どんなに優れた投資商品を選んでも、知識が不足していれば思わぬリスクを抱えてしまう可能性があります。
公務員のように安定した収入基盤を持つ方こそ、将来に備えて金融知識を学び、計画的に資産形成を進めることが大切です。マネーリテラシーを高めることで、以下のような力が身につきます。
- ニュースや経済動向を「自分ごと」として理解できる
- 資産運用に伴うリスクを数値で比較し、冷静に判断できる
- 家計管理やライフプランに基づいた最適な投資判断ができる
学習を続けることは「未来の安心」への投資そのものです。独学だけでなく、専門家やオンラインセミナーを活用して効率的に学ぶのも賢い方法です。
おすすめの学習サービス・無料相談(PR)
資産運用を始めるうえで大切なのは、独学だけに頼らず、信頼できるサービスや専門家の知識を取り入れることです。特に公務員の方にとっては「安定収入を背景にした堅実な投資戦略」や「ライフプランに合わせた将来設計」を学ぶことが重要です。ここでは、初心者でも安心して学べるサービスや、無料で相談できる機会をピックアップしました。自分に合ったスタイルで、お金と知識の両方を育てていきましょう。なお、一部の内容にプロモーションを含みます。詳細は遷移先ページにてご確認いただくようお願いいたします。
証券会社・口座開設
楽天証券
→ 公務員が資産運用を始めるにあたって、楽天証券は非常に魅力的な選択肢です。まず、投資信託の購入手数料が無料である点が大きな強みで、積立投資を気軽に始められます。さらに、楽天カードを使って積立購入を行うと、楽天ポイントが貯まり、そのポイントをそのまま投資に回すこともできるため、資産形成のモチベーションアップにもつながります。
また、楽天証券は2,500本以上の投資信託を取り扱っており、投資先の選択肢が豊富です。さらに、楽天銀行との連携サービス「マネーブリッジ」を活用することで、銀行口座と証券口座の資金移動がスムーズに行えるだけでなく、預金金利の優遇も受けられるというメリットがあります。加えて、公務員の方に人気の高いiDeCo(個人型確定拠出年金)においても、楽天証券は運営管理手数料が業界最低水準で、証券口座と年金口座を一元管理できる利便性が高く評価されています。こうした理由から、特に副業や兼業が制限されている公務員の方にとって、低コストで始めやすく、長期的な資産形成に最適な環境を提供している点で、楽天証券は非常におすすめの証券会社です!
将来に備える第一歩は「知ること」から。楽天証券公式サイトをいますぐチェック!
手数料無料!松井証券のNISA
→ 資産運用や金融リテラシーを学ぶにも、まずは証券会社に口座を作ることが第一歩です。その中でも「松井証券」の100円から始められるNISA・積立投資は、初心者にとって非常に敷居が低く、気軽に実践を始められるのが魅力です。毎月100円からコツコツ積み立てられるため、生活に負担をかけずに長期・分散投資を実践できます。少額から始められることで「失敗しても大きな痛手にならない」という安心感があり、試行錯誤しながら投資の仕組みを学ぶ絶好の機会になります。
さらに、積立の過程で「リスクとリターンの関係」「時間を味方につける効果」「分散投資の重要性」といった金融リテラシーの基礎を自然と体感できます。これは書籍や講座だけでは得られない、“実践を通じた学び”です。
松井証券は老舗の証券会社としての信頼性と、ネット証券ならではの利便性を兼ね備えており、初めて資産運用に挑戦する公務員の方にも安心です。100円からの投資が、将来の大きな安心と知識の財産につながります。
業界最高のポイント還元率!松井証券の『最大1%貯まる投信残高ポイントサービス』![]()
月々1000円からの資産形成ひふみ投信
→ 投資信託「ひふみ」は、小額(1,000円)から始められ、長期保有するほど実質コストが下がる“資産形成応援団”制度が魅力です。たとえば、5年以上保有で年率0.2%相当、10年以上で0.4%相当の信託報酬を還元され、資産の投資効率を高めます。公務員のように収入が安定し、副業制限もある職種にとって、こうした制度の恩恵を受けながら無理なく長期投資できるのは大きなメリットです。
さらに、「ひふみ」は手軽に購入できるつみたて投資に対応しており、NISAの成長投資枠でも利用可能。そのため、公務員が副業として副収入を増やすよりも、制度を活用した資産形成として始めやすい選択肢になります。こうした特徴が、公務員の将来設計にぴったりマッチする理由です。
金融リテラシー学習・資産形成の相談
賢くお金と知識を身につける【マネきゃん/Money Camp】
→ 「マネきゃん/Money Camp」は、公務員という安定した立場を活かした資産運用術を学べる点が大きな魅力です。安定収入を背景にした積立投資や、堅実な長期運用の戦略など、公務員ならではの強みを活かしたノウハウが具体的に紹介されます。また、スマホから気軽に参加できるので、通勤時間や自宅での空き時間を有効に使いながら学習可能。難しい投資理論をやさしく解説してくれるため、初心者でも安心して受講できます。まさに「お金」と「知識」を同時に身につけたい公務員にぴったりのセミナーです。
\公務員にしかできない“資産運用術”を伝授/ 無料セミナーはこちら![]()
年金・貯蓄の無料相談サイト【ガーデン】
→ 「年金っていくらもらえるの?」「老後の資金は足りる?」そんな漠然とした不安に寄り添ってくれるのがガーデンの無料相談サービスです。
専門家に気軽に質問できるので、自分ひとりでは考えきれない部分もスッキリ整理できます。将来の見通しを立てたい方にぴったりです。
オンライン完結型
(PR)資産運用するなら【DMM.com証券】!
→ 投資において、信頼性と使いやすさを重視する公務員にとって、DMM.com証券は理想的な選択肢です。
まず、国内株・米国株、FX、CFDと幅広い商品に対応し、取引手数料が格安または無料(FX・CFD・米国株など)であるため、コストを抑えて資産形成を進められます。さらに、スマホ・PC双方に初心者から上級者まで使える高機能取引ツールが揃っているため、いつでも安心して取引が可能です。加えて、100%信託保全により投資家の資産はDMMの資産とは完全に分離して管理され、万一の際でも保護される体制が整っています。
口座開設もスマホ上で完結し、即日取引が可能な手軽さを備えており、公務員という安定志向の職種にもぴったりです!
【PR】DMM.com証券の新規アカウント登録のお申込みはこちら![]()
まとめ|公務員にとっての資産運用は未来への備えと学び
公務員が株式投資や投資信託に取り組むことは、法律上副業にはあたりません。安心して始められる「資産形成の手段」として、多くの公務員にとって現実的な選択肢となっています。ただし、資産運用の本当の価値は「お金を増やすこと」だけではありません。投資を通じて経済や社会の動きを理解し、金融リテラシーを高める学習の場とすることが、将来の大きな安心につながります。公務員という安定した収入基盤を活かせば、無理のない範囲で着実に資産を育てていくことが可能です。
特に、2024年から拡充された新NISAは、非課税で資産を積み立てられる強力な制度です。長期・積立・分散の基本を守りながら、自分に合った投資スタイルを見つけていきましょう。
公務員にとって資産運用は副業ではなく「未来への備え」であり、同時に学び続けることで得られる自己投資でもあります。今日から小さな一歩を踏み出すことで、数年後、数十年後の安心につながるはずです。