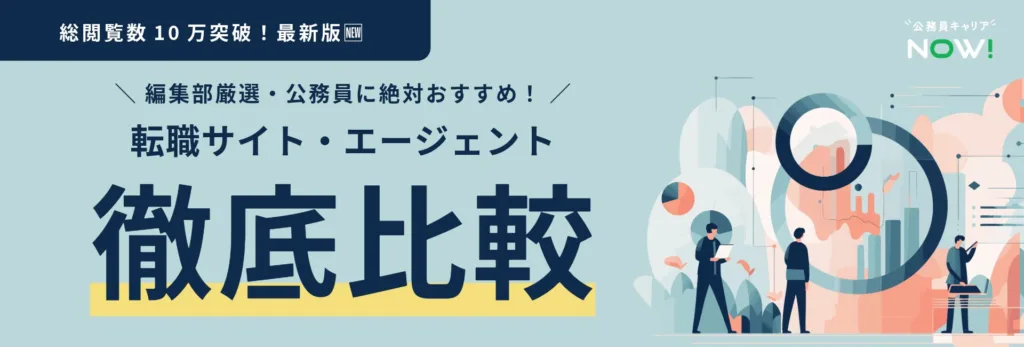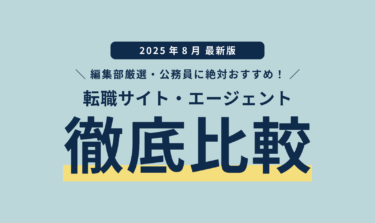VUCA時代における公務員の変化
急激な環境変化、価値観の多様化、AIやテクノロジーの進化――。私たちが生きる現代社会は、「VUCA(ブーカ)」と呼ばれる時代に突入しています。VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、もともとは軍事・経営分野で用いられてきました。
このような先の見えない時代において、行政組織の意思決定やサービス提供にも高度な柔軟性と思考の持続力が求められています。従来の「ルールに従う」「前例を踏襲する」だけでは太刀打ちできない課題が増加し、公務員一人ひとりの思考様式や判断基準の見直しが進んでいます。
こうした中で注目されているのが、「ネガティブ・ケイパビリティ」という新たな能力です。
ネガティブ・ケイパビリティとは何か

ネガティブ・ケイパビリティ(Negative Capability)とは、「答えの出ない状況、不確実な事態の中に耐えて留まり、性急に結論を出さずに思考し続ける能力」を意味します。
この概念は、イギリスの詩人ジョン・キーツによって最初に提唱されました。彼は、理性ではすぐに説明できないものごとを前にしたときに、あえてそれを未確定なままに抱え、創造的な力へと変えていく態度を称賛しました。
現代においては、精神科医のウィルフレッド・ビオンらが、医療や教育、組織マネジメントの領域でこの能力の重要性を再定義し、主に「リーダーシップ」や「複雑な社会課題」に関わる人々に必須の力として位置づけられています。
要するにネガティブ・ケイパビリティとは、「不安定さや不明確さに耐える力」であり、「すぐに答えを出そうとしない勇気」だと言えるでしょう。
VUCAと行政:明確な解がない課題との対峙
現代の行政は、正解が存在しない問いに直面しています。気候変動、人口減少、地域格差、孤独・孤立の問題、AIと倫理…。これらの社会課題は複雑に絡み合い、単一の政策や制度だけで解決できるものではありません。
たとえば、少子化対策において「子育て支援の拡充」だけを進めても、住宅環境・就労支援・教育費・地域の関係性といった複合要因が絡むため、単純な成果につながらないこともあります。
こうした問題に対して、公務員は「急がず、焦らず、長期的視点で考える力」が求められます。ネガティブ・ケイパビリティを発揮することで、行政の現場でも「対話と観察を重ねるアプローチ」「答えの出ないことを前提とした関わり方」が必要不可欠となってきています。
なぜ今、公務員にネガティブ・ケイパビリティが必要なのか
公務員は従来、「確実性」「平等性」「速やかな処理能力」が求められてきました。もちろんこれらは現在でも重要な職責ですが、現代の行政課題には、正解が存在しない領域や、対話を通じて模索しなければならないケースが急増しています。
たとえば住民との協働による地域課題の解決では、住民の意見が多様で、相互に矛盾していることもあります。災害対応や福祉支援では、限られた情報の中で判断を迫られながらも、慎重さが求められる場面も少なくありません。
そのような状況において、即断・即答よりも、「いまは答えが出せないこと」を受け止め、関係者との信頼を築きながら前に進む力。これこそが、ネガティブ・ケイパビリティの本質であり、次世代の公務員像に不可欠な素養なのです。
現場で見られる課題と“短絡的解決”のリスク
一方で、行政の現場には「早く結論を出さなければならない」「完璧な正解が求められている」といった空気が蔓延しやすい傾向もあります。
たとえば、SNS等での批判を恐れるあまり、政策判断が萎縮し、“前例踏襲”に陥る。あるいは、現場の声を聴く余裕がないまま、「とにかく説明がつく答え」を出そうとする。こうした短絡的対応が繰り返されると、結果として問題の本質に迫れず、表面的な「処理」で終わってしまうことも少なくありません。
それを防ぐには、「一時的な不安定さ」をチーム全体で受け止め、「考え続けること」を正しく評価する組織文化が必要です。公務員にとって、ネガティブ・ケイパビリティは個人のスキルであると同時に、「行政の質」を底上げする文化的素地でもあるのです。
ネガティブ・ケイパビリティを育むための研修・制度設計
公務員がネガティブ・ケイパビリティを実践的に身につけるには、個人の意識改革だけでなく、組織としての育成の仕組みが必要です。
具体的には、以下のような要素を含む制度・研修が効果的とされています:
- ケースメソッド型研修:明確な答えのない行政事例を題材にし、参加者同士で議論・内省する
- 越境学習の導入:民間企業・NPO・地域団体など異分野との交流を通じて視野を広げる
- 対話重視の職場文化:上司・部下・横の関係性の中で“問いを開いたまま議論できる”環境づくり
- 心理的安全性の確保:「すぐ答えを出さなくても良い」と感じられる職場づくり
特に注目されているのは「問いを深めるスキル」。目の前の課題に即答するのではなく、「そもそも何が問題なのか?」「その前提は本当に妥当なのか?」といった一段深い視点を養う研修が求められています。
年代・立場別:ネガティブ・ケイパビリティの実践法
ネガティブ・ケイパビリティは、すべての年代・職層にとって重要な資質です。ただし、立場によってその実践方法や影響範囲は異なります。
若手職員の場合
若手公務員は、配属当初から正解を出すことに囚われがちです。あえて「わからないことを受け入れながら考え続ける」プロセスを尊重するマインドが必要です。メンター制度や振り返り面談が、有効な育成の場になります。
中堅職員の場合
中堅層は、現場の調整役や企画立案の中心を担う立場です。「結論急げ」と周囲に圧をかけるのではなく、あえてチームに“ゆらぎ”を持たせて、深い議論ができる時間をつくるファシリテーター的役割が求められます。
管理職・リーダーの場合
管理職には、「不安定な状態に組織全体で耐える」ための支柱的役割が求められます。部下からの“すぐに答えがほしい”という声に対しても、あえて「考える余白」を与えることで、組織の思考力を底上げする存在となります。
先進自治体での取り組み事例
長野県:キャリア形成と協働文化の推進
長野県庁が公表する「職員育成基本方針」では、キャリアパス設計と評価制度の改訂を通じて、ネガティブ・ケイパビリティ的な力を育む試みが進んでいます。30代・40代・50代それぞれのライフステージに応じてワークショップや原体験振返りなどの研修が実施され、自身の志や価値観を深く問い直す仕組みが整備されています。
さらに、長野県ではNPOや企業など多様な主体と連携し、「協働コーディネートデスク」を県庁内に設置。協働を円滑に進めるための調整や相談機能を担うことで、行政職員が「すぐに答えを出さない対話型の関係性」を日常的に実践できる環境づくりを推進しています
✅ 参考記事 ▶︎ 職員育成において「問いるワークショップ」「評価制度の再設計」など、思考の質を高める取り組み|長野県
塩尻市(長野県):地域まるごと人材戦略のモデル
長野県塩尻市では、NPOや金融機関、大学、市職員など多様な主体が連携する「塩尻の人事部コンソーシアム」を発足。地域として人的資本強化に取り組む先進的なモデルとして注目されています。
これは公務員職員のみならず、民間・NPOと共に「問い続ける文化」を醸成しながら、協働による地域づくりを実践する取り組みと言えるでしょう。
✅ 参考記事 ▶︎ 【全国初の事例】地域ぐるみで地域の人材課題解決に向き合う!塩尻市における「地域の人事部」連携協定締結のお知らせ|NPO法人MEGURU
千葉県・千葉市:教育領域でのファシリテーション強化
千葉県と千葉市教育委員会は、教育公務員の定期研修においてファシリテーションや主体的対話力の育成を重要視しています。
「社会教育士」養成課程では、ファシリテーションやコーディネート能力が明記され、行政的視点から問いを開いた対話が促進されています。
✅ 参考記事 ▶︎ ファシリテーションを公教育の育成指標に導入|千葉県
自治体横断:越境学習や多様人材連携の取り組み
各自治体では、NPO・企業・大学などと公務員が交流する越境学習型制度も進行中。長野県の協働推進や塩尻市のコンソーシアムは、その代表例であり、VUCA時代の柔軟で開かれた行政文化を育むモデルとなっています。
導入のためのステップと注意点
ネガティブ・ケイパビリティを組織的に育むには、段階的な仕掛けが効果的です。
① 言語化と共有:まずはこの概念を組織で理解・定義する
② 小さな実践:職場内で“問い続ける時間”を確保してみる
③ 評価の見直し:「答えを急がず考え抜いたこと」が評価される指標づくり
④ 上司のモデル化:管理職自らが不安定な状況に立ち向かう姿勢を示す
注意点としては、「考え続ける=決めないこと」と誤解されないようにすることです。ネガティブ・ケイパビリティはあくまで「判断の質」を高めるためのプロセスであり、“逃げ”ではありません。
必要な場面ではしっかり意思決定を下す胆力と両立させることが重要です。
まとめ:持続可能な行政を支える新しい能力
正解がなく、前例も通じない。そんな時代において、公務員に求められるのは、あらゆる不確実性に耐えながらも、市民や現場と向き合い続ける“静かな強さ”です。
ネガティブ・ケイパビリティは、その「静かな強さ」の土台をつくる力です。行政職員一人ひとりが、不安や矛盾の中に居続ける力を持ち、組織としてそれを支えられる文化があれば、VUCA時代のどんな困難にも、希望とともに対応していけるはずです。
いま、公務員のキャリアにおいて最も大切なのは、「すぐに正解を出す」ことではなく、「問う力」「考え抜く力」を育てること。そして、そのプロセスを信じられる仲間とともに働くことではないでしょうか。